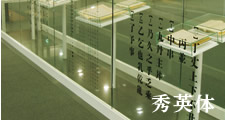一〇〇年目の書体づくり
「秀英体 平成の大改刻」の記録
一〇〇年目の書体づくり――はじめに
大日本印刷の前身である秀英舎は、1876(明治9)年、「活版印刷により、文明社会の発展に貢献する」という志を持って創業されましたが、印刷技術の変化にともなって、活字鋳造と組版事業を2003(平成15)年3月に終了させるに至りました。127年に及ぶ長い歴史に幕をひくわけですから、伝統文化を終わらせてしまうような深い感慨と将来への重い責任を強く感じました。
丁度この時期、「秀英体」の書体デザインの変遷を体系化して記録に残そうと、活字・印刷史の研究家である片塩二朗氏に調査・研究をお願いしていました。秀英体とは、秀英舎が創業して間もなく、独自に開発した書体です。東京築地活版製造所の「築地体」と並んで金属活字書体の双璧と評され、多くの出版物に使われてきました。片塩氏からの調査報告書は、500ページにも及ぶ膨大なものでした。これは、後世に残すべきものとして、書籍化することにしました。それが、2004年に刊行された『秀英体研究』です。
『秀英体研究』編集の際に片塩氏は、「秀英体は延々と開発を続けてきたために、コピー複写を繰り返したように、『弱々しい文字』となり、『か細い形姿』となってしまった。殊に、1970年代以降は組版のコンピューター化とともにデジタルフォントとして展開され、さらに、1990年代には出版社からの要望に応えて電子書籍にも応用された結果、『秀英体は、本来の姿ではなくなっている』」と指摘されました。
また、「この調査に参加・協力をしたDNPの社員が、活字と書物をなによりも愛し、秀英体に深い愛着と誇りを抱いていることを確認することができた。この報告書をきっかけに、これからのDNPを担う若者達による秀英体の再生を願う」と語られていたことにも心を動かされました。
私は、そこに込められた思いを検討し、また片塩さんと直接お話をして、秀英体の改刻に踏み切ることを決意しました。創業期から受け継がれてきた「秀英体」という貴重な文化的資産を守り、未来につなげていかなくてはならないと感じたからです。
こうして、「平成の大改刻」が2005(平成17)年から始まりました。改刻にあたり、プロジェクトでは、そもそも「秀英体らしい」とはどういうことなのか、から議論を始め、新しいメディアに対応しながら、なにを守り、なにを改めるのか、などの議論と試行錯誤が繰り返されました。7年の月日をかけて、改刻はひとまず終了しました。
この改刻の軌跡を記録に留めることで、たとえば将来にまったく新しいメディアが台頭して、秀英体が再び姿を整えなくてはならなくなったとき、この記録が判断のよすがになることを願っています。また、書体の開発・研究に従事する方々の一助となり、将来への一灯となれば幸いです。
最後になりましたが、長いあいだ、秀英体を見守り続け、今回の大改刻プロジェクトにご協力いただいた多くの皆様に心より感謝申し上げます。
大日本印刷株式会社
社長 北島義俊